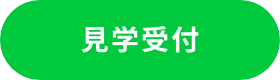高校無償化の所得制限撤廃について
高校無償化の所得制限が撤廃されることになりました。
これをめぐっては賛成、反対さまざまな意見があるようです。新聞社などの行った世論調査によると概ね若い世代を中心に賛成が多いものの、私学も含めて無償化することには一部に根強い抵抗があるようにも見受けられます。また日本経済新聞が経済学者を対象として行ったアンケート調査では賛否が分かれるものの7割が反対との結果も出ています。
今月はこうした意見を踏まえ、自分自身の考えを整理してお伝えしていきたいと思います。
まずは現行制度の確認から。
高校無償化は大きく分けて国による「就学支援金制度」と、それを補完する各自治体による「軽減補助制度」からなりますが、今回所得制限の撤廃が決まったのは国の就学支援金制度の方です。
(軽減補助制度が今後どうなっていくのはまだ不透明です。)
これまでの就学支援金制度は次の二つからなります。
1 年収910万円以下の家庭には公立高校の年間授業料に相当する11万8800円が支給される。
2 私学に通う年収590万円以下の家庭には年間39万6000円を上限として年間授業料分が支給される。
2で「上限」としているのは私学の授業料は学校により異なるので、これを超える場合、その分は家庭の負担になるということです。
そして今回決まったのは次の二つです。
1については2025年度4月から910万円以下という制限をなくす。
2については2026年度4月から590万円以下の制限をなくし、支給の上限を45万7000円に引き上げる。
世論調査等を見る限り公立高校の所得制限撤廃に関して反対する人は少数です。一方、意見が大きく分かれるのは私学も含めて所得制限を無くすことについてであり、反対意見も多く述べられています。
そして反対されている方の意見を見ると、その理由は次の二つに大別されるように思います。
A 高額所得の家庭まで支援する必要はない。(もっと別のことに予算を使うべき)
B 私学に生徒が流れ公立高校が衰退する。(私学の受験競争も激化し、教育費が塾などに流れる)
これに対し自分自身は基本的に所得制限の撤廃に賛成です。理由としては私学である生野学園に通う生徒の家庭の負担が減ることはもちろんですが、それだけではありません。
以下、A, Bの意見を検討する中でその理由を説明させていただきます。
まずAの意見の背景には「教育にかかる費用は子どもを持つ家庭が本来負担すべきだが、所得の少ない家庭にとっては負担が大きいので支援が必要だ」という考えがあるように思います。支援金の目的はあくまで所得の低い家庭に対する「救済」にあるという考えです。それゆえに「負担できる所得があるのなら自分たちで負担すべきだ」という主張になるのではないでしょうか。
これに対し自分は「教育にかかる費用は子どもを持つ家庭だけでなく、広く社会全体で負担すべき」と思っています。
その理由は次のとおりです。
そもそも一つの社会が存続していくためには、次世代を担う子どもたちを育てていく必要があります。特にお互いが自由に生きることを認め、自分たちの代表を選挙で選ぶ民主主義の社会であれば、それを担うことのできる知識や判断力を持った子どもたちを育てることが欠かせません。そのために生まれたのが義務教育なわけですが、今日のようにより複雑になった社会であれば小中だけでなく高校での教育も受ける必要性があると思います。また大きな変化が予想されるこれからの社会に対しては、公立学校のような一律の教育だけでなく、さまざまな考えに基づくより多様な教育も必要になってきます。そうであれば私学も含めた学校教育を「公教育」として社会全体で支えていくべきであり、それが結果として社会全体の利益につながるのではないでしょうか。
所得の高い家庭にはより多くの税金を納めていただき、そうして集めたお金で無償で受けられる公教育の制度を運営していく、そしてその制度に関しては誰もが平等に適用されるべきだというのが自分の考えです。
ただし、私学の独自性を鑑みれば、支給される上限を超える費用がかかっても自分たちが考える教育を実現し、その分は家庭に負担していただくという選択はあって当然だと思います。実際に今回設定された上限を超えている私学も少なくないのではないでしょうか。不登校を経験した子どもたちを対象とした少人数制の学校である生野学園の授業料も(寮費食費は除く)年間で54万円ですから8万3000円分は家庭の負担をお願いすることになります。
次にBの意見に対して。
確かに今回の所得制限の撤廃だけでは生徒は私学に流れると思います。しかし、だからと言って「撤廃するな」というのではなく、公立高校がより魅力的になるような対策を講じることこそが本来めざすべき方向なのではないでしょうか。
当然そのためにはさまざまな施作が必要になります。まずは教員の待遇改善が必要になるでしょう。現在のように教員に多くの負担をかけ、成り手が減少しているような状況では公立学校の変化は望めないと思います。そしてこれまで一律を旨としてきた学校の制度そのものの見直しも必要になるでしょう。そのためには現場の先生方の自由度をより高めることで特色ある教育を実現していくことが重要になると思います。
そしてたとえ定員割れしたからといってすぐに予算を削ったり、統廃合してしまうのは避けるべきです。公立であるがゆえに採算にとらわれることなく丁寧に一人ひとりに対応してくれる学校であることが認識されれば公立の人気は復活していくのではないでしょうか。また私学が進出できない人口の少ない地域の子どもたちの教育の機会を保障するためには公立の高校を維持していくことが欠かせません。たとえ採算が合わなくても教育の機会均等を実現するためには公費を投入するべきなのです。
いずれにせよ公立校にしかできないことを探っていくことが重要になりますが、それを実施するためには相当の予算が必要です。
もしそのための予算配分をしないのであればBの意見の懸念は現実化されてしまうと思います。
ですからこの点に関する自分の立場は「条件付きで賛成」ということになります。
所得制限の撤廃にあたってはもう一つ必要なことがあると思っています。
それは公教育を公費で賄う以上、そのめざすところを明確化すべきだということです。現行の学習指導要領の「主体的、対話的で深い学び」という方向は基本的に正しいと思っていますが、これからの社会の変化に向けて子どもたちが身につけるべき力をもう少しはっきりとさせるべきではないでしょうか。自分としてはこの先AIが進化し、社会のあらゆる場所に進出していく状況を考えれば、判断をAIに任せてしまうのではなく、広く他者の意見に耳を傾け、論理的に考え、人としてバランスの取れた判断を下すことのできる力をつけていくことが喫緊の課題ではないかと感じています。
次期学習指導要領の検討が始まっているようですが、こうした議論を深め、公教育のめざすべき方向性が正しく示されることを期待しています。
これをめぐっては賛成、反対さまざまな意見があるようです。新聞社などの行った世論調査によると概ね若い世代を中心に賛成が多いものの、私学も含めて無償化することには一部に根強い抵抗があるようにも見受けられます。また日本経済新聞が経済学者を対象として行ったアンケート調査では賛否が分かれるものの7割が反対との結果も出ています。
今月はこうした意見を踏まえ、自分自身の考えを整理してお伝えしていきたいと思います。
まずは現行制度の確認から。
高校無償化は大きく分けて国による「就学支援金制度」と、それを補完する各自治体による「軽減補助制度」からなりますが、今回所得制限の撤廃が決まったのは国の就学支援金制度の方です。
(軽減補助制度が今後どうなっていくのはまだ不透明です。)
これまでの就学支援金制度は次の二つからなります。
1 年収910万円以下の家庭には公立高校の年間授業料に相当する11万8800円が支給される。
2 私学に通う年収590万円以下の家庭には年間39万6000円を上限として年間授業料分が支給される。
2で「上限」としているのは私学の授業料は学校により異なるので、これを超える場合、その分は家庭の負担になるということです。
そして今回決まったのは次の二つです。
1については2025年度4月から910万円以下という制限をなくす。
2については2026年度4月から590万円以下の制限をなくし、支給の上限を45万7000円に引き上げる。
世論調査等を見る限り公立高校の所得制限撤廃に関して反対する人は少数です。一方、意見が大きく分かれるのは私学も含めて所得制限を無くすことについてであり、反対意見も多く述べられています。
そして反対されている方の意見を見ると、その理由は次の二つに大別されるように思います。
A 高額所得の家庭まで支援する必要はない。(もっと別のことに予算を使うべき)
B 私学に生徒が流れ公立高校が衰退する。(私学の受験競争も激化し、教育費が塾などに流れる)
これに対し自分自身は基本的に所得制限の撤廃に賛成です。理由としては私学である生野学園に通う生徒の家庭の負担が減ることはもちろんですが、それだけではありません。
以下、A, Bの意見を検討する中でその理由を説明させていただきます。
まずAの意見の背景には「教育にかかる費用は子どもを持つ家庭が本来負担すべきだが、所得の少ない家庭にとっては負担が大きいので支援が必要だ」という考えがあるように思います。支援金の目的はあくまで所得の低い家庭に対する「救済」にあるという考えです。それゆえに「負担できる所得があるのなら自分たちで負担すべきだ」という主張になるのではないでしょうか。
これに対し自分は「教育にかかる費用は子どもを持つ家庭だけでなく、広く社会全体で負担すべき」と思っています。
その理由は次のとおりです。
そもそも一つの社会が存続していくためには、次世代を担う子どもたちを育てていく必要があります。特にお互いが自由に生きることを認め、自分たちの代表を選挙で選ぶ民主主義の社会であれば、それを担うことのできる知識や判断力を持った子どもたちを育てることが欠かせません。そのために生まれたのが義務教育なわけですが、今日のようにより複雑になった社会であれば小中だけでなく高校での教育も受ける必要性があると思います。また大きな変化が予想されるこれからの社会に対しては、公立学校のような一律の教育だけでなく、さまざまな考えに基づくより多様な教育も必要になってきます。そうであれば私学も含めた学校教育を「公教育」として社会全体で支えていくべきであり、それが結果として社会全体の利益につながるのではないでしょうか。
所得の高い家庭にはより多くの税金を納めていただき、そうして集めたお金で無償で受けられる公教育の制度を運営していく、そしてその制度に関しては誰もが平等に適用されるべきだというのが自分の考えです。
ただし、私学の独自性を鑑みれば、支給される上限を超える費用がかかっても自分たちが考える教育を実現し、その分は家庭に負担していただくという選択はあって当然だと思います。実際に今回設定された上限を超えている私学も少なくないのではないでしょうか。不登校を経験した子どもたちを対象とした少人数制の学校である生野学園の授業料も(寮費食費は除く)年間で54万円ですから8万3000円分は家庭の負担をお願いすることになります。
次にBの意見に対して。
確かに今回の所得制限の撤廃だけでは生徒は私学に流れると思います。しかし、だからと言って「撤廃するな」というのではなく、公立高校がより魅力的になるような対策を講じることこそが本来めざすべき方向なのではないでしょうか。
当然そのためにはさまざまな施作が必要になります。まずは教員の待遇改善が必要になるでしょう。現在のように教員に多くの負担をかけ、成り手が減少しているような状況では公立学校の変化は望めないと思います。そしてこれまで一律を旨としてきた学校の制度そのものの見直しも必要になるでしょう。そのためには現場の先生方の自由度をより高めることで特色ある教育を実現していくことが重要になると思います。
そしてたとえ定員割れしたからといってすぐに予算を削ったり、統廃合してしまうのは避けるべきです。公立であるがゆえに採算にとらわれることなく丁寧に一人ひとりに対応してくれる学校であることが認識されれば公立の人気は復活していくのではないでしょうか。また私学が進出できない人口の少ない地域の子どもたちの教育の機会を保障するためには公立の高校を維持していくことが欠かせません。たとえ採算が合わなくても教育の機会均等を実現するためには公費を投入するべきなのです。
いずれにせよ公立校にしかできないことを探っていくことが重要になりますが、それを実施するためには相当の予算が必要です。
もしそのための予算配分をしないのであればBの意見の懸念は現実化されてしまうと思います。
ですからこの点に関する自分の立場は「条件付きで賛成」ということになります。
所得制限の撤廃にあたってはもう一つ必要なことがあると思っています。
それは公教育を公費で賄う以上、そのめざすところを明確化すべきだということです。現行の学習指導要領の「主体的、対話的で深い学び」という方向は基本的に正しいと思っていますが、これからの社会の変化に向けて子どもたちが身につけるべき力をもう少しはっきりとさせるべきではないでしょうか。自分としてはこの先AIが進化し、社会のあらゆる場所に進出していく状況を考えれば、判断をAIに任せてしまうのではなく、広く他者の意見に耳を傾け、論理的に考え、人としてバランスの取れた判断を下すことのできる力をつけていくことが喫緊の課題ではないかと感じています。
次期学習指導要領の検討が始まっているようですが、こうした議論を深め、公教育のめざすべき方向性が正しく示されることを期待しています。