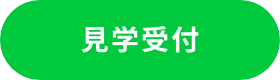池のこと
中学男子寮の裏には小さな池があります。今月はこの池にまつわるお話にお付き合いください。
生野学園は傾斜地を造成して建てられたため、各建物の裏側はちょっとした崖になっています。そして造成前の中学男子寮の敷地には小さな水の流れがあったので、現在も寮裏の崖下から湧水が出ているのです。そのままにしておくと周囲が水浸しになってしまうため、溝を作って敷地の下まで流すようになっていますが、それでも湧水の周りは常に湿った状態でした。
実は現在の中学男子寮は、以前は高校の女子寮として使用されていました。中学生がこの寮に移転してきた際、子どもたちに「湧水を利用して池を作らないか」という提案をしてみたところ、釣りが好きな生徒も何人かいて「池があれば釣った魚を飼える」と賛同してくれたのです。
まずは池のための穴を掘りです。ところが、この土地は結構大きな石だらけで手作業ではなかなか手強いことがわかり、結局は小型のユンボを使って穴を掘ってもらいました。しかし掘っただけでは池にはなりません。水を入れても地面に吸収されてしまうのです。何とか吸水を防ぐ方法を考えなければなりません。
いろいろ調べた結果、ゴムシートを使う方法が手っ取り早いと分かりましたが、経年劣化で穴が空いてしまった場合の修理の手間を考えると採用する気にはなれませんでした。コンクリートで固めてしまう方法もありましたが、ひび割れのリスクが高いのでこれも却下です。そんな時、「ベントナイト」という物質があり土壌の水漏れ防止に使われていることを知りました。ベントナイトは粉状の物質ですが水を含むと粘土になります。これを土に混ぜて池の底に粘土層を作れば水の吸収を抑えられるのではないかと考えたのです。実際にベントナイトを購入し、土と混ぜて粘土状にしたものを池の底に貼り付けると、底からの水漏れはすぐに止まりました。しかし、手強かったのが横からの水漏れです。横壁に粘土層を作るのが難しく、ある程度水が溜まってくると穴が空き水が漏れてしまうのです。そのため何度も粘土を貼り直し、再び水を入れる作業を繰り返しました。
ある日、池を遠くから見ると様子が変わっており、近づいてみると水が満水になっていました。やっと池が完成したのです。おそらく、ベントナイトを含む土が水漏れ部分の奥に少しずつ溜まり、自然と穴が塞がれたのではないかと思います。
完成した池でさまざまなことを試してみました。
変わった魚が欲しいと思いオヤニラミという魚を購入して放しましたが、大雨が降った後いなくなってしまいました。大雨が降ると池と溝の間に水路ができてしまうので、そこから逃げ出したのかもしれません。川エビを入れたこともありましたが、これもいつの間にかいなくなりました。ホテイアオイという水草を浮かべた時はなんと一晩で鹿に食べられてしまいました。アマゴも放しました。この魚は渓流魚なので夏場の水温上昇に耐えられるか懸念されましたが、何とか夏は乗り切ったのです。ところが、これはいけるかと思った矢先に台風による増水でいなくなってしまいました。
結果的に、定着したのは近くの川で釣ってきたカワムツという魚と、どこからかやってきたカエルでした。あとは池にやって来るさまざまな昆虫たちです。数年後、ある生徒が「イモリを飼いたい」と言い出したため、イモリが住みやすいように浅瀬を増設し、捕まえてきたイモリを放しました。するとこのイモリも定着しました。
特に餌を与えているわけではないので、この3種の生物は池にやって来る昆虫などを食べて生きているようです。そして何年も生息し続けているところをみると、繁殖もしているのではと考えられます。
こうして、池は小さな生態系――ビオトープとなりました。
この環境に、大型魚を入れてみたこともあります。
釣り好きの生徒がスタッフと一緒に釣ってきた70cmほどの大きな雷魚を池に放し、その子の希望で学園祭で「展示」したのです。池には餌になる小魚がたくさんいるので、人の手で餌をやる必要はないと考えましたが、一冬を越したものの、最終的には死んでしまいました。池に浮いている姿を発見したときには、すでに一部を動物に食べられていました。池が小さく、すばしっこいカワムツを捕食するのが困難で弱っていったのかもしれません。
また、川で釣ってきた鯉を二度放したこともありました。
一匹目は大雨による増水の時に逃げ出してしまったようです。後から溝を探しても発見できませんでした。この溝には鯉が生息できるような広い場所はないため、おそらく逃げ出した後で動物に食べられてしまったのではないかと思います。可哀想なことをしました。
もう一匹は半年ほど池にいました。冬場で増水がなかったのが幸いしたのかもしれません。
池の中には鯉の餌になるような植物はなく、わずかな昆虫だけでは生きていけないと思ったので鯉の餌を買ってきて与えました。ところが、その餌をカワムツが横取りするのです。餌が豊富になるとカワムツも大型化していきます。そして一旦大型化してしまうとその魚体を維持するために餌をやり続けなければならなくなります。つまり人間が餌やりという形で介入することでこれまで維持されてきた生態系のバランスが崩れかけてきたのです。最終的に鯉は川に戻すことにしました。池の中で逃げ回る鯉を捕獲するのは大変でしたが、三人がかりで何とか浅瀬に追い込み、網で掬って、釣ってきた川に戻しました。この池は大型魚には適さないというのが結論です。
人の手で作った場所ですが、そこに適した生き物たちが小さな自然を形成し再生していく、この過程からいろいろと学ばせてもらいました。
実は学園にはもう一つ池があります。高校校舎の前の公園の中にある池です。
これは高校の10期生たちが先代の安平校長と作ったものです。今もサマースクールでの「アマゴ掴み」や学園祭の「釣り堀」に利用させてもらっています。
今、この池には学園祭の釣り堀で生き残ったアマゴたちが住んでいます。この池には沢で取水した水を給水しているので、水質的にはアマゴの生息に適していますが、餌が足りません。小さな池に飛んでくる昆虫だけでは全然足りないのです。そのためほぼ毎日人の手による餌やりが必要で、学園祭以降ずっと続けているのです。
毎日餌やりをして魚たちが順調に育っていく様子をみると嬉しい反面どこか「不自然なことをしている」という感覚があるのも否めません。この魚たちが自然に生きていける広い川に放してやるのもよいかなと考えている次第です。
生野学園は傾斜地を造成して建てられたため、各建物の裏側はちょっとした崖になっています。そして造成前の中学男子寮の敷地には小さな水の流れがあったので、現在も寮裏の崖下から湧水が出ているのです。そのままにしておくと周囲が水浸しになってしまうため、溝を作って敷地の下まで流すようになっていますが、それでも湧水の周りは常に湿った状態でした。
実は現在の中学男子寮は、以前は高校の女子寮として使用されていました。中学生がこの寮に移転してきた際、子どもたちに「湧水を利用して池を作らないか」という提案をしてみたところ、釣りが好きな生徒も何人かいて「池があれば釣った魚を飼える」と賛同してくれたのです。
まずは池のための穴を掘りです。ところが、この土地は結構大きな石だらけで手作業ではなかなか手強いことがわかり、結局は小型のユンボを使って穴を掘ってもらいました。しかし掘っただけでは池にはなりません。水を入れても地面に吸収されてしまうのです。何とか吸水を防ぐ方法を考えなければなりません。
いろいろ調べた結果、ゴムシートを使う方法が手っ取り早いと分かりましたが、経年劣化で穴が空いてしまった場合の修理の手間を考えると採用する気にはなれませんでした。コンクリートで固めてしまう方法もありましたが、ひび割れのリスクが高いのでこれも却下です。そんな時、「ベントナイト」という物質があり土壌の水漏れ防止に使われていることを知りました。ベントナイトは粉状の物質ですが水を含むと粘土になります。これを土に混ぜて池の底に粘土層を作れば水の吸収を抑えられるのではないかと考えたのです。実際にベントナイトを購入し、土と混ぜて粘土状にしたものを池の底に貼り付けると、底からの水漏れはすぐに止まりました。しかし、手強かったのが横からの水漏れです。横壁に粘土層を作るのが難しく、ある程度水が溜まってくると穴が空き水が漏れてしまうのです。そのため何度も粘土を貼り直し、再び水を入れる作業を繰り返しました。
ある日、池を遠くから見ると様子が変わっており、近づいてみると水が満水になっていました。やっと池が完成したのです。おそらく、ベントナイトを含む土が水漏れ部分の奥に少しずつ溜まり、自然と穴が塞がれたのではないかと思います。
完成した池でさまざまなことを試してみました。
変わった魚が欲しいと思いオヤニラミという魚を購入して放しましたが、大雨が降った後いなくなってしまいました。大雨が降ると池と溝の間に水路ができてしまうので、そこから逃げ出したのかもしれません。川エビを入れたこともありましたが、これもいつの間にかいなくなりました。ホテイアオイという水草を浮かべた時はなんと一晩で鹿に食べられてしまいました。アマゴも放しました。この魚は渓流魚なので夏場の水温上昇に耐えられるか懸念されましたが、何とか夏は乗り切ったのです。ところが、これはいけるかと思った矢先に台風による増水でいなくなってしまいました。
結果的に、定着したのは近くの川で釣ってきたカワムツという魚と、どこからかやってきたカエルでした。あとは池にやって来るさまざまな昆虫たちです。数年後、ある生徒が「イモリを飼いたい」と言い出したため、イモリが住みやすいように浅瀬を増設し、捕まえてきたイモリを放しました。するとこのイモリも定着しました。
特に餌を与えているわけではないので、この3種の生物は池にやって来る昆虫などを食べて生きているようです。そして何年も生息し続けているところをみると、繁殖もしているのではと考えられます。
こうして、池は小さな生態系――ビオトープとなりました。
この環境に、大型魚を入れてみたこともあります。
釣り好きの生徒がスタッフと一緒に釣ってきた70cmほどの大きな雷魚を池に放し、その子の希望で学園祭で「展示」したのです。池には餌になる小魚がたくさんいるので、人の手で餌をやる必要はないと考えましたが、一冬を越したものの、最終的には死んでしまいました。池に浮いている姿を発見したときには、すでに一部を動物に食べられていました。池が小さく、すばしっこいカワムツを捕食するのが困難で弱っていったのかもしれません。
また、川で釣ってきた鯉を二度放したこともありました。
一匹目は大雨による増水の時に逃げ出してしまったようです。後から溝を探しても発見できませんでした。この溝には鯉が生息できるような広い場所はないため、おそらく逃げ出した後で動物に食べられてしまったのではないかと思います。可哀想なことをしました。
もう一匹は半年ほど池にいました。冬場で増水がなかったのが幸いしたのかもしれません。
池の中には鯉の餌になるような植物はなく、わずかな昆虫だけでは生きていけないと思ったので鯉の餌を買ってきて与えました。ところが、その餌をカワムツが横取りするのです。餌が豊富になるとカワムツも大型化していきます。そして一旦大型化してしまうとその魚体を維持するために餌をやり続けなければならなくなります。つまり人間が餌やりという形で介入することでこれまで維持されてきた生態系のバランスが崩れかけてきたのです。最終的に鯉は川に戻すことにしました。池の中で逃げ回る鯉を捕獲するのは大変でしたが、三人がかりで何とか浅瀬に追い込み、網で掬って、釣ってきた川に戻しました。この池は大型魚には適さないというのが結論です。
人の手で作った場所ですが、そこに適した生き物たちが小さな自然を形成し再生していく、この過程からいろいろと学ばせてもらいました。
実は学園にはもう一つ池があります。高校校舎の前の公園の中にある池です。
これは高校の10期生たちが先代の安平校長と作ったものです。今もサマースクールでの「アマゴ掴み」や学園祭の「釣り堀」に利用させてもらっています。
今、この池には学園祭の釣り堀で生き残ったアマゴたちが住んでいます。この池には沢で取水した水を給水しているので、水質的にはアマゴの生息に適していますが、餌が足りません。小さな池に飛んでくる昆虫だけでは全然足りないのです。そのためほぼ毎日人の手による餌やりが必要で、学園祭以降ずっと続けているのです。
毎日餌やりをして魚たちが順調に育っていく様子をみると嬉しい反面どこか「不自然なことをしている」という感覚があるのも否めません。この魚たちが自然に生きていける広い川に放してやるのもよいかなと考えている次第です。