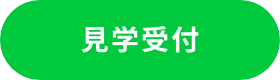ピザ窯完成の報告

①この状態が長く続く
2023年1月の「雑感」で中学校の開校記念として一年がかりで作った石窯のことをお話させていただきました。そしてその最後の部分で実はピザ用の新たな石窯を作り始めていることをお伝えし「完成のあかつきにはこのサイトで報告させていただこうと思っています。」と宣言していました。しかしその後さまざまな事情から作業は中断してしまい、右の写真①の状態が長く続いていたのです。
ところが、昨年になってある生徒の熱心な後押しもあり、ようやく重い腰を上げることになりました。そして昨年度中にレンガ150個の購入と、まだ出来ていなかった入り口部分のアーチ状の木枠を完成させるところまでたどり着き、今年度からは「ピザ窯を完成させて学園祭でピザを売る部」=通称「ピザ部」も発足し、いよいよ本格的な石窯作りがスタートしたのです。

①この状態が長く続く

② レンガを積んでいく作業

③ くさび状に加工したレンガ

④ 上部のレンガの形状

⑤ ドームとアーチの接合部分

⑥ レンガ積みが完了
まずは右の写真②のように木枠に沿ってレンガを並べ、隙間を耐火セメントで埋め、固定していく作業です。
ここで使ったレンガは「半マス」と呼ばれる半分サイズのものです。これを使用するのは天井の曲面に合わせるためにはなるべく小さいもののほうがやりやすいからです。
実は、ピザ窯作りの一番の難しさは「レンガをドーム状の曲面に合わせる」ということにあります。
その理由を少し説明しておきます。
以前に作った石窯はトンネル状のものでした。この天井も曲面ではありますが、これは伸ばしてしまえば平面になるものです。(実際、作成に使用した木枠はベニヤ板を曲げて作りました)数学の言葉を使うと、現状は曲面でも伸ばせば平面になる曲面は「曲率が0である」といいます。曲がっていても「曲率」は0なのです。
これに対し、ドーム状(半球)の表面は平面に伸ばすことが出来ません。伸び縮するゴムのようなもので出来ていれば無理やり伸ばしていくことはできますが、端の部分は限りなく長くなってしまいます。これは世界地図で極に近い部分が異様に大きくなってしまうこと(例えばグリーンランドの異様な大きさ)を見ればわかると思います。数学の言葉で言うとドームの表面は「曲率がプラスの値をとる」のです。
(参考までにラッパ状の曲面の曲率はマイナスになります)
曲率が0であれば、その曲面に合わせてレンガを並べるのは比較的簡単です。平面と違ってレンガ同士の間に隙間は出来ますが、曲がっている方向が一方向なので出来る隙間も一方向にしか生じません。その隙間を耐火セメントで塞いでいけば良いのです。今回作ったピザ窯でも入り口のアーチ部分はそれにあたります。
これに対し曲率がプラスの曲面にレンガを並べる場合は隙間が上下と左右の2方向に生じます。この隙間を小さくするためにはレンガのサイズをなるべく小さくする必要があるのです。
先ほどの写真②はドームの下段の部分を作っているものですが、このあたりは周の半径が大きいので生じる隙間は比較的小さく、作業もスムーズに進みました。
ところが、上部に行くにつれ半径が小さくなると、生じる隙間は大きくなり、埋めようとしても耐火レンガが流れ出してしまうようになります。こうなると直方体の半マスのレンガでは対応できません。レンガそのものを加工する必要が出てくるのです。
右の写真③はレンガをくさび状に加工して並べたものです。上辺に比べると下辺が短くなっているのがお分かりになるでしょうか?
これがもっと上部になると写真④のようにはっきりと長さに差が生じてくるのです。
この加工は電動グラインダーにダイヤモンド刃を取り付けて切断していくものですが、かなり危険な作業になります。勢いよく破片が飛び散るので目にはゴーグルを着用し、手には作業用の革手袋をはめて行いますが、注意を怠ると刃が引っ掛かってキックバックし大けがをする危険があります。さすがにこの作業には生徒にはやらせるわけにはいかないので、夏休み中にすべて自分がやりました。
あともう一つ難しかったのが写真⑤の入り口のアーチ部分と本体のドーム部分が交わる部分です。
二つの部分がうまく組み合わさるように、それぞれのレンガを加工していく必要があるのです。どのような形状にすれば良いのかはあらかじめ想像しづらいので、少し削っては試しに合わせてみるという作業を繰り返して何とか組むことが出来ました。
2学期のはじめにはレンガを積んでいく作業はほぼ完了し、最後にみんなで7角形に削ったレンガをてっぺんに埋め込んで終了しました。写真⑥
ここで使ったレンガは「半マス」と呼ばれる半分サイズのものです。これを使用するのは天井の曲面に合わせるためにはなるべく小さいもののほうがやりやすいからです。
実は、ピザ窯作りの一番の難しさは「レンガをドーム状の曲面に合わせる」ということにあります。
その理由を少し説明しておきます。
以前に作った石窯はトンネル状のものでした。この天井も曲面ではありますが、これは伸ばしてしまえば平面になるものです。(実際、作成に使用した木枠はベニヤ板を曲げて作りました)数学の言葉を使うと、現状は曲面でも伸ばせば平面になる曲面は「曲率が0である」といいます。曲がっていても「曲率」は0なのです。
これに対し、ドーム状(半球)の表面は平面に伸ばすことが出来ません。伸び縮するゴムのようなもので出来ていれば無理やり伸ばしていくことはできますが、端の部分は限りなく長くなってしまいます。これは世界地図で極に近い部分が異様に大きくなってしまうこと(例えばグリーンランドの異様な大きさ)を見ればわかると思います。数学の言葉で言うとドームの表面は「曲率がプラスの値をとる」のです。
(参考までにラッパ状の曲面の曲率はマイナスになります)
曲率が0であれば、その曲面に合わせてレンガを並べるのは比較的簡単です。平面と違ってレンガ同士の間に隙間は出来ますが、曲がっている方向が一方向なので出来る隙間も一方向にしか生じません。その隙間を耐火セメントで塞いでいけば良いのです。今回作ったピザ窯でも入り口のアーチ部分はそれにあたります。
これに対し曲率がプラスの曲面にレンガを並べる場合は隙間が上下と左右の2方向に生じます。この隙間を小さくするためにはレンガのサイズをなるべく小さくする必要があるのです。
先ほどの写真②はドームの下段の部分を作っているものですが、このあたりは周の半径が大きいので生じる隙間は比較的小さく、作業もスムーズに進みました。
ところが、上部に行くにつれ半径が小さくなると、生じる隙間は大きくなり、埋めようとしても耐火レンガが流れ出してしまうようになります。こうなると直方体の半マスのレンガでは対応できません。レンガそのものを加工する必要が出てくるのです。
右の写真③はレンガをくさび状に加工して並べたものです。上辺に比べると下辺が短くなっているのがお分かりになるでしょうか?
これがもっと上部になると写真④のようにはっきりと長さに差が生じてくるのです。
この加工は電動グラインダーにダイヤモンド刃を取り付けて切断していくものですが、かなり危険な作業になります。勢いよく破片が飛び散るので目にはゴーグルを着用し、手には作業用の革手袋をはめて行いますが、注意を怠ると刃が引っ掛かってキックバックし大けがをする危険があります。さすがにこの作業には生徒にはやらせるわけにはいかないので、夏休み中にすべて自分がやりました。
あともう一つ難しかったのが写真⑤の入り口のアーチ部分と本体のドーム部分が交わる部分です。
二つの部分がうまく組み合わさるように、それぞれのレンガを加工していく必要があるのです。どのような形状にすれば良いのかはあらかじめ想像しづらいので、少し削っては試しに合わせてみるという作業を繰り返して何とか組むことが出来ました。
2学期のはじめにはレンガを積んでいく作業はほぼ完了し、最後にみんなで7角形に削ったレンガをてっぺんに埋め込んで終了しました。写真⑥

② レンガを積んでいく作業

③ くさび状に加工したレンガ

④ 上部のレンガの形状

⑤ ドームとアーチの接合部分

⑥ レンガ積みが完了

⑦ 小屋の側面から出した煙突

⑧ 断熱材の取り付け

⑨ 耐火モルタルで全体を覆う
次の作業は煙突作りです。写真⑦のようにピザ窯を設置した小屋の側面に煙突を立てましたが、当初はこの部分が木に覆われており、部員たちでかなり太い枝を伐採しました。
これも結構たいへんな作業でした。
次はいよいよ内部に残った木枠を燃やしてしまう作業です。幸い木枠が無くなってもレンガが崩れることはありませんでした。ところがレンガと耐火セメントの間にけっこう隙間が残っていて、そこから煙が漏れ出してきたので、後日この隙間を埋める作業を実施しました。
この状態でも十分に機能するので、いちおう「完成」なのですが、長時間にわたって使用する場合の効率を考えると、断熱をしておいた方がベターです。最初の石窯で使った断熱材の余りを「いつか使うかもしれない」と思いずっととっておいたので、これをピザ窯の表面に貼り付けます。そして、さらにそれを金属の網で覆って固定していくのです。(写真⑧)
この作業でも曲率プラスの曲面に合わせる困難さに悩まされました。断熱材も網もそれぞれいくつかのピースに切り分けドームを覆っていく必要がありました。
最後はその上に断熱モルタルを塗り付けていく作業です。(写真⑨)
これが終了して、長かったピザ窯作りもついに完成です。
ちなみに断熱材の効果はてきめんで、3時間以上燃やしても表面は手で触れる程度の温度にしか上がりません。
あとはいよいよ学園祭でのピザ販売です。
店の名前はすでに決まっていて ”Pizzeria Stella Alta”。イタリア語でStellaは「星」、Altaは「高い」という意味なので和名は「高星ピザ屋」ということになります。
試作を何度かしてだいぶうまく焼けるようになったと思います。しかし当日は数をこなさなければならないのでまだまだ不安はぬぐえません。
なんとかうまくいくように願っています。
これも結構たいへんな作業でした。
次はいよいよ内部に残った木枠を燃やしてしまう作業です。幸い木枠が無くなってもレンガが崩れることはありませんでした。ところがレンガと耐火セメントの間にけっこう隙間が残っていて、そこから煙が漏れ出してきたので、後日この隙間を埋める作業を実施しました。
この状態でも十分に機能するので、いちおう「完成」なのですが、長時間にわたって使用する場合の効率を考えると、断熱をしておいた方がベターです。最初の石窯で使った断熱材の余りを「いつか使うかもしれない」と思いずっととっておいたので、これをピザ窯の表面に貼り付けます。そして、さらにそれを金属の網で覆って固定していくのです。(写真⑧)
この作業でも曲率プラスの曲面に合わせる困難さに悩まされました。断熱材も網もそれぞれいくつかのピースに切り分けドームを覆っていく必要がありました。
最後はその上に断熱モルタルを塗り付けていく作業です。(写真⑨)
これが終了して、長かったピザ窯作りもついに完成です。
ちなみに断熱材の効果はてきめんで、3時間以上燃やしても表面は手で触れる程度の温度にしか上がりません。
あとはいよいよ学園祭でのピザ販売です。
店の名前はすでに決まっていて ”Pizzeria Stella Alta”。イタリア語でStellaは「星」、Altaは「高い」という意味なので和名は「高星ピザ屋」ということになります。
試作を何度かしてだいぶうまく焼けるようになったと思います。しかし当日は数をこなさなければならないのでまだまだ不安はぬぐえません。
なんとかうまくいくように願っています。

⑦ 小屋の側面から出した煙突

⑧ 断熱材の取り付け

⑨ 耐火モルタルで全体を覆う