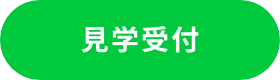次期学習指導要領にむけた「論点整理」について
先日、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の教育課程企画特別部会で行われてきた13回にわたる議論の「論点整理」が発表されました。
この会議は2030年から導入される次期学習指導要領をどのようなものにするかを有識者を集めて検討するもので、ここで示された方向にそって新しい学習指導要領が策定されていきます。ですからこれは今後の日本の学校教育を決定づけるとても重要なものなのです。
論点整理自体は100ページ以上にわたる膨大なものですが、その冒頭で「目指すべき3つの方向性」が提示されているので引用しておきます。
「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を「みんな」で育むため、
①「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
②多様性の包摂(Equity)
③実現可能性の確保(Feasibility)
の3つの方向性を踏まえて議論を行う。これらの3つの方向性に基づく改善は、教育課程内外のあらゆる方策を用いつつ、三位一体で具現化されるべきものである。」
論点整理ではこの後、3つの方向性について詳しい説明が展開されていくのですが、簡単にまとめておくと、
①は現行の学習指導要領でも目指されている「主体的・対話的で深い学び」をよりいっそう確実なものに「実装」していくということであり、
②は多様な個性や特性、背景を有する子どもたち一人ひとりが、①で示されるような深い学びを獲得していけるような仕組み・体制を整えていくということ。
③は①と②が単なるスローガンにならないように、教育課程の内容だけでなく、教育環境、生徒や教員のおかれた状況、学校の体制などを含めて見直し、改革していくことで実現可能性を確保するということだと思います。
論点整理を一読し、自分としては日本の学校教育の改革にむけて概ね良い方向性が示されたのではと歓迎しています。以下、その理由をお話していきます。
実は現行の学習指導要領の問題についてはこれまでこの「雑感」で何度か取り上げさせてもらいました。その時、主張したことは次のことです。
この会議は2030年から導入される次期学習指導要領をどのようなものにするかを有識者を集めて検討するもので、ここで示された方向にそって新しい学習指導要領が策定されていきます。ですからこれは今後の日本の学校教育を決定づけるとても重要なものなのです。
論点整理自体は100ページ以上にわたる膨大なものですが、その冒頭で「目指すべき3つの方向性」が提示されているので引用しておきます。
「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を「みんな」で育むため、
①「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
②多様性の包摂(Equity)
③実現可能性の確保(Feasibility)
の3つの方向性を踏まえて議論を行う。これらの3つの方向性に基づく改善は、教育課程内外のあらゆる方策を用いつつ、三位一体で具現化されるべきものである。」
論点整理ではこの後、3つの方向性について詳しい説明が展開されていくのですが、簡単にまとめておくと、
①は現行の学習指導要領でも目指されている「主体的・対話的で深い学び」をよりいっそう確実なものに「実装」していくということであり、
②は多様な個性や特性、背景を有する子どもたち一人ひとりが、①で示されるような深い学びを獲得していけるような仕組み・体制を整えていくということ。
③は①と②が単なるスローガンにならないように、教育課程の内容だけでなく、教育環境、生徒や教員のおかれた状況、学校の体制などを含めて見直し、改革していくことで実現可能性を確保するということだと思います。
論点整理を一読し、自分としては日本の学校教育の改革にむけて概ね良い方向性が示されたのではと歓迎しています。以下、その理由をお話していきます。
実は現行の学習指導要領の問題についてはこれまでこの「雑感」で何度か取り上げさせてもらいました。その時、主張したことは次のことです。
1.「主体的・対話的で深い学び」には全く賛成であるが、その実現にあたっては解決しなければならない問題がある。
2. 特に現行の指導要領は「知識を効率良く教え込む教育」を前提に形成されてきたものであるため、いくぶん改善されてきた面はあるものの、いまだに内容が膨大かつ網羅的でありすぎる。
3. そして、これまで「教える教育」をしてきた教師が「主体的・対話的な学び」に移行していくためには「意識の変革」や「新たなスキルの習得」が必要であり、それには時間的・精神的な余裕が必要である。
2. 特に現行の指導要領は「知識を効率良く教え込む教育」を前提に形成されてきたものであるため、いくぶん改善されてきた面はあるものの、いまだに内容が膨大かつ網羅的でありすぎる。
3. そして、これまで「教える教育」をしてきた教師が「主体的・対話的な学び」に移行していくためには「意識の変革」や「新たなスキルの習得」が必要であり、それには時間的・精神的な余裕が必要である。
これらの問題に対して今回の論点整理はしっかり解決の方向性を示していると思います。
まず、学習指導要領の内容については次のことが言われています。
「各教科等の「中核的な概念の深い理解」「複雑な課題の解決」を中心に、学習指導要領の目標・内容の一層の「構造化」を図る・・(後略)」
「その際、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、各教科等の中核的な概念等の獲
得に重点を置くために必要な学習内容を検討したり、必要に応じた精選を行う方向
で検討すべき」
これだけだと分かりにくい文章ですが、自分なりに「意訳」すれば、
「『中核的概念の深い理解』=『基礎固め』と『複雑な課題の解決』=『実際の場面で使える応用力』をはっきり分けて、それぞれの目標と内容を明確にしていく。
さらに『中核的概念の深い理解』のための『根幹』をなす内容と付随する『枝葉』の部分を明確に分け『枝葉』の部分については『精選』=『必要性の低いものは削ってもよい』ということ」だと思います。
こうした方向性が示された背後には、今の子どもたちの学習において基礎的な内容が必ずしも定着していないことに対する危機感があると思います。
論点整理の中でも触れられていますが、例えば小学校での分数計算では分数の意味をしっかり理解していない子どもたちがかなり見受けられるのです。論点整理の資料によると「『2分の1』と『3分の1』のどちらが大きいか?」という問題に対する正答率が4年生で22.4%、5年生でも49.7%にとどまっているのです。
本来であれば、分数の意味という「中核的概念」をしっかり理解した上で、「それでは分数のたし算やかけ算はどのように行えばよいのか」という理解に進むべきなのですが、実際の教育現場では時間的制約もあり、とりあえず計算を出来るようにするために、例えば分数のかけ算であれば「分子同士、分母同士をかければよい」割り算であれば「ひっくり返してかける」といった安易な「教え方」に流されてしまう危険性があることは否めません。
もしそうだとすると「主体的・対話的で深い学び」とはまったくかけ離れたものになってしまいます。
こうした状況に陥らないように「習得すべき中核的概念」を明確化し、それをしっかり理解するために学ぶ内容を整理・精選していくべきだという方向性が示されたのだと思います。
実際の指導要領はこれから各教科のワーキンググループで策定されていきますが、明解でスリムなものになることを期待しています。
さらに論点整理の第3章では「多様な個性や特性、背景を有する子どもたちに対応するために、これまでよりも柔軟な教育課程編成を可能にすべき」という方向性も示されています。
これは先ほどの分数の例で言えば、分数の意味という中核概念が定着していない子どもに対しては標準よりも多くの時間をかけて良いし、逆にすでに定着している子どもであれば標準の時間よりも縮小して、その分を「複雑な課題の解決」にまわすといったことを可能にすべきだということだと思います。もちろん教育課程の編成が完全に自由になるわけではありませんが、ある程度の柔軟性と現場の裁量をまかせる部分を増やす仕組みが検討されているのです。
そしてこれは「学びの多様化学校」として「カリキュラムの個別化」を導入している生野学園の目指す方向とも重なるものと考えています。
次は教師の精神的・時間的な余裕の問題についてです。
論点整理の第5章では「過度な負担・負担感が生じにくい在り方を追求することや、教師と子供の双方に『余白』を創出し、豊かな教育活動に繋げることが必要」とされ以下の5つの課題が提示されています。
まず、学習指導要領の内容については次のことが言われています。
「各教科等の「中核的な概念の深い理解」「複雑な課題の解決」を中心に、学習指導要領の目標・内容の一層の「構造化」を図る・・(後略)」
「その際、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、各教科等の中核的な概念等の獲
得に重点を置くために必要な学習内容を検討したり、必要に応じた精選を行う方向
で検討すべき」
これだけだと分かりにくい文章ですが、自分なりに「意訳」すれば、
「『中核的概念の深い理解』=『基礎固め』と『複雑な課題の解決』=『実際の場面で使える応用力』をはっきり分けて、それぞれの目標と内容を明確にしていく。
さらに『中核的概念の深い理解』のための『根幹』をなす内容と付随する『枝葉』の部分を明確に分け『枝葉』の部分については『精選』=『必要性の低いものは削ってもよい』ということ」だと思います。
こうした方向性が示された背後には、今の子どもたちの学習において基礎的な内容が必ずしも定着していないことに対する危機感があると思います。
論点整理の中でも触れられていますが、例えば小学校での分数計算では分数の意味をしっかり理解していない子どもたちがかなり見受けられるのです。論点整理の資料によると「『2分の1』と『3分の1』のどちらが大きいか?」という問題に対する正答率が4年生で22.4%、5年生でも49.7%にとどまっているのです。
本来であれば、分数の意味という「中核的概念」をしっかり理解した上で、「それでは分数のたし算やかけ算はどのように行えばよいのか」という理解に進むべきなのですが、実際の教育現場では時間的制約もあり、とりあえず計算を出来るようにするために、例えば分数のかけ算であれば「分子同士、分母同士をかければよい」割り算であれば「ひっくり返してかける」といった安易な「教え方」に流されてしまう危険性があることは否めません。
もしそうだとすると「主体的・対話的で深い学び」とはまったくかけ離れたものになってしまいます。
こうした状況に陥らないように「習得すべき中核的概念」を明確化し、それをしっかり理解するために学ぶ内容を整理・精選していくべきだという方向性が示されたのだと思います。
実際の指導要領はこれから各教科のワーキンググループで策定されていきますが、明解でスリムなものになることを期待しています。
さらに論点整理の第3章では「多様な個性や特性、背景を有する子どもたちに対応するために、これまでよりも柔軟な教育課程編成を可能にすべき」という方向性も示されています。
これは先ほどの分数の例で言えば、分数の意味という中核概念が定着していない子どもに対しては標準よりも多くの時間をかけて良いし、逆にすでに定着している子どもであれば標準の時間よりも縮小して、その分を「複雑な課題の解決」にまわすといったことを可能にすべきだということだと思います。もちろん教育課程の編成が完全に自由になるわけではありませんが、ある程度の柔軟性と現場の裁量をまかせる部分を増やす仕組みが検討されているのです。
そしてこれは「学びの多様化学校」として「カリキュラムの個別化」を導入している生野学園の目指す方向とも重なるものと考えています。
次は教師の精神的・時間的な余裕の問題についてです。
論点整理の第5章では「過度な負担・負担感が生じにくい在り方を追求することや、教師と子供の双方に『余白』を創出し、豊かな教育活動に繋げることが必要」とされ以下の5つの課題が提示されています。
1. 授業時数の適正化(授業時数の縮小)
2. 授業時数と平準化(週当たりコマ数の縮小)
3.「厚い教科書をすべて教える」からの脱却
4. 構造化・表形式化・デジタル化を通じた余白の創出
5. 高校入学者選抜の在り方の改善
2. 授業時数と平準化(週当たりコマ数の縮小)
3.「厚い教科書をすべて教える」からの脱却
4. 構造化・表形式化・デジタル化を通じた余白の創出
5. 高校入学者選抜の在り方の改善
それぞれ決して簡単な課題ではありませんが、これらを検討・見直していくことで生徒、教師双方の負担軽減を図るとされており、これも全く正しい方向性だと思っています。
余談になりますが、この「余白の創出」は実質「ゆとり」に近いもの思っています。しかし、かつての「ゆとり教育」への批判を考えると、さすがに「ゆとり」を使うわけにはいかず、この言葉が生み出されたのではないでしょうか。どなたが提案されたのかは知りませんがうまい言葉を思いつくものと感心させられました。
論点整理の内容は膨大で、今回取り上げたのはほんの一部にすぎません。ただ全体を一読して感じたのは、かつてなく踏み込んだ内容であり、現状に対する認識とそれに対する改革の方向性ともに共感が持てるものが多いということです。13回にわたり深い議論を繰り広げられてきた委員の皆様と、それを取りまとめた文科省の担当の方に敬意を表したいと思います。
余談になりますが、この「余白の創出」は実質「ゆとり」に近いもの思っています。しかし、かつての「ゆとり教育」への批判を考えると、さすがに「ゆとり」を使うわけにはいかず、この言葉が生み出されたのではないでしょうか。どなたが提案されたのかは知りませんがうまい言葉を思いつくものと感心させられました。
論点整理の内容は膨大で、今回取り上げたのはほんの一部にすぎません。ただ全体を一読して感じたのは、かつてなく踏み込んだ内容であり、現状に対する認識とそれに対する改革の方向性ともに共感が持てるものが多いということです。13回にわたり深い議論を繰り広げられてきた委員の皆様と、それを取りまとめた文科省の担当の方に敬意を表したいと思います。