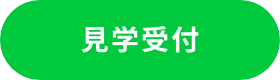庭について
-- 波心庭と無隣庵 --
自分の楽しみの一つとして庭を観に行くことがあります。わざわざそのためだけに出かけることはあまりありませんが、出先でちょっと時間があったりすると近くの庭を訪れてみるのです。
庭にはじめて興味を持ったのはかなり古く中高生のころでした。当時は東京に住んでおり、修学旅行の行き先は中高ともに京都・奈良、そこでは数々の素晴らしい庭と出会う機会に恵まれたのです。一つ一つの庭からは作庭した人の世界観のようなものが感じられ、対面したり、あるいは中に入り込んだりする中で作者がその庭に込めた思いが伝わってくるように感じました。また「この造形にはどんな意味があるんだろう」とあれこれ考えてみるのも面白い経験だったのです。これは自分にとってかなり大きなことだったようで、修学旅行後に課せられた感想文ではともに庭のことを書いた記憶があります。
以来、機会を見つけては庭を見に行ったり、庭に関する書籍を読んだりしてきたのですが、実は「お気に入り」の庭が二つあるので今月はそれを紹介しようと思います。
庭にはじめて興味を持ったのはかなり古く中高生のころでした。当時は東京に住んでおり、修学旅行の行き先は中高ともに京都・奈良、そこでは数々の素晴らしい庭と出会う機会に恵まれたのです。一つ一つの庭からは作庭した人の世界観のようなものが感じられ、対面したり、あるいは中に入り込んだりする中で作者がその庭に込めた思いが伝わってくるように感じました。また「この造形にはどんな意味があるんだろう」とあれこれ考えてみるのも面白い経験だったのです。これは自分にとってかなり大きなことだったようで、修学旅行後に課せられた感想文ではともに庭のことを書いた記憶があります。
以来、機会を見つけては庭を見に行ったり、庭に関する書籍を読んだりしてきたのですが、実は「お気に入り」の庭が二つあるので今月はそれを紹介しようと思います。

波心庭(一部)
一つは京都の東福寺光明院の波心庭です。
これは作庭家の重森三玲(しげもりみれい)の作品で、昭和14年に作られたということなので京都の庭としては比較的新しい部類に入るものです。
初めて訪れたのは30年近く前になります。当時、生野学園では学期の終わりに「特別時間割」といって普段は出来ないような体験的な学習を実施していました。その特別時間割の一つとして自分が企画したのが「庭を観に行く」という授業で、協力してくれたスタッフとともに車2台を連ねて10名ほどの生徒を連れて東福寺を訪れたのです。
初めて観た波心庭はとても斬新でした。系譜としては水を用いず石や砂を使って山水を表現する枯山水と言われる庭に属するものですが、これまで見た古典的な枯山水とはかなり違った印象を受けました。
写真を見ていただければわかるように、苔の生えた陸地と海を思わせる白砂が緩やかな曲線をなして構成され、そこに大小たくさんの石が配されています。特徴的なのは多くの石が地面に直立するように置かれていることで、そのためどこか「地面から生えてきた」ような印象も与えます。相当に「変わった」庭ではありますが、かといって特に「奇をてらった」ような印象はなく、全体としては「自然さ」も感じるのです。これだけの石を配置して微妙なバランスを維持し「自然さ」を感じさせるのは、背後に相当に綿密で入念な計算があったのではと想像します。いったい重森三玲がどのようにしてこんな庭を思いついてのか不思議でなりませんが、人を引きつける魅力を持った庭であることは間違いないと思います。
また庭そのものは石と砂と苔からなるので、苔の色合いの変化を除けば不変なのですが、周囲にはサツキやカエデの木が植えられているので四季によって庭の風情は変化していきます。これもこの庭の魅力を引き立てており、連れて行った生徒の一人が「今度は秋に来てみたい」と言っていたのが思い起こされます。
これは作庭家の重森三玲(しげもりみれい)の作品で、昭和14年に作られたということなので京都の庭としては比較的新しい部類に入るものです。
初めて訪れたのは30年近く前になります。当時、生野学園では学期の終わりに「特別時間割」といって普段は出来ないような体験的な学習を実施していました。その特別時間割の一つとして自分が企画したのが「庭を観に行く」という授業で、協力してくれたスタッフとともに車2台を連ねて10名ほどの生徒を連れて東福寺を訪れたのです。
初めて観た波心庭はとても斬新でした。系譜としては水を用いず石や砂を使って山水を表現する枯山水と言われる庭に属するものですが、これまで見た古典的な枯山水とはかなり違った印象を受けました。
写真を見ていただければわかるように、苔の生えた陸地と海を思わせる白砂が緩やかな曲線をなして構成され、そこに大小たくさんの石が配されています。特徴的なのは多くの石が地面に直立するように置かれていることで、そのためどこか「地面から生えてきた」ような印象も与えます。相当に「変わった」庭ではありますが、かといって特に「奇をてらった」ような印象はなく、全体としては「自然さ」も感じるのです。これだけの石を配置して微妙なバランスを維持し「自然さ」を感じさせるのは、背後に相当に綿密で入念な計算があったのではと想像します。いったい重森三玲がどのようにしてこんな庭を思いついてのか不思議でなりませんが、人を引きつける魅力を持った庭であることは間違いないと思います。
また庭そのものは石と砂と苔からなるので、苔の色合いの変化を除けば不変なのですが、周囲にはサツキやカエデの木が植えられているので四季によって庭の風情は変化していきます。これもこの庭の魅力を引き立てており、連れて行った生徒の一人が「今度は秋に来てみたい」と言っていたのが思い起こされます。

波心庭(一部)
もう一つの「お気に入り」の庭は同じく京都の無隣庵です。
こちらは波心庭と違って水や植物、樹木をふんだんに使い、庭内を回遊できる形式の庭になります。
もともと無隣庵は明治の元勲である山縣有朋の別荘で、その庭は山縣自身の支持のもとで庭師の小川治兵衛が明治27年〜29年にかけて作庭したものです。系譜としては池泉回遊式庭園と呼ばれるものに属しますが、これも伝統的なものとはだいぶ異なるものになっています。この形式の伝統的な庭は中央に大きな池を配し、その周りに築山、石、樹木、橋などで名勝を模した景観を造形し、周囲に巡らせた園路にそって回遊できるようにしたものです。
ところが無隣庵にはそもそも池はありません。かわりに東山を借景とした庭の正面には芝生を配した明るい広場があり、そこに小川が流れているのです。そして、この小川をたどっていくと樹木を配した森のような部分が続き、やがて最奥に作られた三段の滝にたどり着きます。その最上部からは琵琶湖疎水から取り入れられた豊富な水が流れ落ちているのです。
こちらは波心庭と違って水や植物、樹木をふんだんに使い、庭内を回遊できる形式の庭になります。
もともと無隣庵は明治の元勲である山縣有朋の別荘で、その庭は山縣自身の支持のもとで庭師の小川治兵衛が明治27年〜29年にかけて作庭したものです。系譜としては池泉回遊式庭園と呼ばれるものに属しますが、これも伝統的なものとはだいぶ異なるものになっています。この形式の伝統的な庭は中央に大きな池を配し、その周りに築山、石、樹木、橋などで名勝を模した景観を造形し、周囲に巡らせた園路にそって回遊できるようにしたものです。
ところが無隣庵にはそもそも池はありません。かわりに東山を借景とした庭の正面には芝生を配した明るい広場があり、そこに小川が流れているのです。そして、この小川をたどっていくと樹木を配した森のような部分が続き、やがて最奥に作られた三段の滝にたどり着きます。その最上部からは琵琶湖疎水から取り入れられた豊富な水が流れ落ちているのです。

無隣庵パンフレットより転載
池の周りを巡るのとは違い、小川に沿って奥に分け入っていき、最深部にたどり着くとまた小川にそって帰ってくるという構成になっているのです。しかも取り入れられ、造形されているのは「名勝」のような景観ではなく、とても身近な自然の風景なのです。
たぶん池泉回遊式庭園が造られた根源には極楽浄土を模すという発想があり、救済を求めるという前近代的な思いがあります。それに比べると明治につくられた無隣庵の庭はとても近代的で、浄土ではなく身近な里山的自然に安らぎを求める発想が感じられるのです。たぶんそれがこの庭の親しみやすさにつながっているのでしょう。
そうした視点にたつと波心庭もまたとても近代的な庭に思えます。
伝統的な枯山水には仏教思想が背景にあって、煩悩をたつように庭からも極力余計なものを削って「無の境地」に至ろうとする傾向があります。波心庭もお寺の庭ですからたぶん仏教的な意味合いは込められているはずですが、あの大量の石を見ると「極限まで削る」という発想は感じられません。あそこで表現されているのは極度に抽象化された形ではありますが、なんらかの自然や自然の持つ力のようなものなのではないかという気がするのです。そしてそれがこの庭の不思議な魅力につながっているのではないかと想像します。
重森三玲、山縣有朋、小川治兵衛いずれも日本の近代化の中で生きた人たちです。特に山縣にいたってはそれを主導した人物でもあります。こうした人たちが伝統を受け継ぎつつも新たな試みを成し遂げた成果として、波心庭と無隣庵は貴重な存在だと思います。どちらも公開されているので機会があれば観られることをお勧めします。(無隣庵は予約が必要になったようです。)
最後に、今回庭の話をしようと思ったきっかけについてお話しておきます。
この雑感も先月で100回目を迎え、実は毎月ネタ探しに苦労しています。
そんな中で立ち寄った本屋でまさに「庭の話」という本が目に入ったのです。著者は宇野常寛氏。名前だけは知っていたけど本を読んだりYoutube配信を見たことはありませんでした。それでも題名に引かれて手に取ってみると、けっこう面白そうだったので読んでみることにしたのです。それと同時に、自分も今回は「庭の話」をしてみようかなとなったわけです。
宇野さんの本はまだ読み始めたばかりなのでなんとも言えませんが、機会があれば感想をお話ししてみようかと思います。
たぶん池泉回遊式庭園が造られた根源には極楽浄土を模すという発想があり、救済を求めるという前近代的な思いがあります。それに比べると明治につくられた無隣庵の庭はとても近代的で、浄土ではなく身近な里山的自然に安らぎを求める発想が感じられるのです。たぶんそれがこの庭の親しみやすさにつながっているのでしょう。
そうした視点にたつと波心庭もまたとても近代的な庭に思えます。
伝統的な枯山水には仏教思想が背景にあって、煩悩をたつように庭からも極力余計なものを削って「無の境地」に至ろうとする傾向があります。波心庭もお寺の庭ですからたぶん仏教的な意味合いは込められているはずですが、あの大量の石を見ると「極限まで削る」という発想は感じられません。あそこで表現されているのは極度に抽象化された形ではありますが、なんらかの自然や自然の持つ力のようなものなのではないかという気がするのです。そしてそれがこの庭の不思議な魅力につながっているのではないかと想像します。
重森三玲、山縣有朋、小川治兵衛いずれも日本の近代化の中で生きた人たちです。特に山縣にいたってはそれを主導した人物でもあります。こうした人たちが伝統を受け継ぎつつも新たな試みを成し遂げた成果として、波心庭と無隣庵は貴重な存在だと思います。どちらも公開されているので機会があれば観られることをお勧めします。(無隣庵は予約が必要になったようです。)
最後に、今回庭の話をしようと思ったきっかけについてお話しておきます。
この雑感も先月で100回目を迎え、実は毎月ネタ探しに苦労しています。
そんな中で立ち寄った本屋でまさに「庭の話」という本が目に入ったのです。著者は宇野常寛氏。名前だけは知っていたけど本を読んだりYoutube配信を見たことはありませんでした。それでも題名に引かれて手に取ってみると、けっこう面白そうだったので読んでみることにしたのです。それと同時に、自分も今回は「庭の話」をしてみようかなとなったわけです。
宇野さんの本はまだ読み始めたばかりなのでなんとも言えませんが、機会があれば感想をお話ししてみようかと思います。