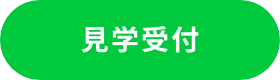規範意識の形成について
昔と今の不登校の子どもたちの違いの一つに「規範意識」の強弱があるように思います。
初期のころの不登校の子どもたちは「こうあるべきだ」「こうあってはいけない」という規範意識を強く持っていました。そのため高い理想を掲げそれを目指して頑張るが、どうしても無理をするのでやがて疲弊していき、達成できない自分を責めたり、さまざまな身体症状を発して登校できなくなるという過程をたどることが多かったのです。
これに対し、今のこどもたちはそれほど規範意識が高いわけではなく、不登校の理由は多様化し、中心は友人関係の問題に移行してきたように思います。
ただ「規範意識の低下」は不登校の子どもたちに限った話ではなく、もっと広い日本の子どもたち全体の傾向のようにも感じます。試しにネットで「規範意識、低下」と検索すると、現状や対策をめぐって多くの議論が展開されており、多くの人、特に教育関係の人たちの間ではこうした問題意識が共有されているのではないでしょうか。
ではその原因はなにか? あるいはそもそも「規範意識」はどのように形成されるのか?
今月はそのことについて少し考えてみようと思います。
まず問題とする「規範意識」について明確にしておきます。ここで言う「規範意識」は単に「決められた規則を守る」という「遵法精神」のことではなく、自らの内面に形成された「こうあるべき」「こうあってはならない」という行動を律する道徳律のことで、「ルールを守る」という意味での規範意識はその一部をなすものです。
人間はこうした規範意識を成長の過程で身に付けていくわけですが、その形成過程の解明に先鞭をつけたのが心理学者フロイトです。
フロイトは人間の心にはエス(無意識)、自我、超自我の三つの領域があり、このうちの超自我が道徳律を担う部分だとしました。そしてこの超自我がどのように形成されるかを説明したのがエディプス・コンプレックスといわれるものです。
以下、話の流れに必要な範囲で簡単に説明しておきます。
3歳〜6歳の男児は母親に対する愛情から母を独占したいという欲求を抱きます。そのため競争相手としての父親に敵意や対抗心を持つようになりますが、同時に強大な存在としての父親から罰せられるのではないかという恐怖を抱きます。この葛藤を克服するために男児は乗り越えられない存在としての父親に、敵対心を抱きながらも「父親のようになろう」と同一視するようになります。この過程で父親の価値観、行動原理を自らの中に取り込むことで超自我が形成されていくというのです。
重要なのは「敵対心と恐怖を抱きながらも同一視する」という複雑な心理過程(コンプレックス)だと思います。(日本ではコンプレックスというと「劣等感」のようにとらえている傾向がありますが、一筋縄にはいかない複雑な心の状態を意味するととらえるべきでしょう。)
フロイトは女児の場合についても説明していますが、男児に比べ超自我の形成が不完全であるとされるなど、どうしても男性中心、父性原理に偏った印象はぬぐいきれません。エディプス・コンプレックスはフロイトの生きた時代背景、個人的経験が色濃く反映されたもので、一面の真理はついているもののこれだけでは普遍的な理論にはなりえない印象です。
そのためフロイトの理論を補完したり、批判するさまざまな理論が形成されて行きます。
その中の一つにフロイトの弟子である心理学者の古澤平作が提唱した東洋人の心理過程を説明する「阿闍世(アジャセ)コンプレックス」があります。
これについても簡単に説明しておきます。
阿闍世は仏典に出てくる古代インドのマガタ国の王子です。阿闍世はその出生の経緯から自らの存在価値を認められていないと思い母親である韋提希(イダイケ)夫人を恨み、攻撃するようになります。ところが阿闍世が重病にかかったとき、攻撃されていた韋提希夫人が献身的な看病をしたことでなんとか阿闍世は回復します。これにより阿闍世の中に自らを許し受け入れてくれた母に対する「もうしわけなかった」という懺悔の心が芽生えていきます。
このように母親との関係の中で受け入れて欲しいという欲求と、それがかなえられないことから来る恨みと攻撃、そうした葛藤を経た後での許しと受容という複雑な心理過程の中で罪悪意識が形成されていくとするのです。
厳格な父性原理をベースとするエディプス・コンプレックスと受容する母性原理をベースとする阿闍世コンプレックスはどちらか一方が正しいわけでなく、お互いを補うものととらえるべきで、子どもたちの状況によりそれぞれの見方をすればよいのではないでしょうか。
また規範意識の形成は当然この二つの過程に限られるわけではなく、じっさい子どもたちはさまざまな時期に、さまざまな形や経緯でで自らの規範意識を形成しくのでしょう。
ただ、この二つは今もなお子どもたちの規範意識の形成にいくつかの大切な視点を与えていると思っています。
まず重要なのはどちらの理論も子どもたちの規範意識は心の複雑な動き、相反する感情が揺れ動く葛藤を経て初めて形成されるとしていることです。規範は親が一方的に教え込むものではなく、親との深い関係のなかで子どもの中に生まれてくるものだということです。
そしてどちらの理論も直接には子どもと父親、母親との関係に関するものですが、これについては生物学的なつながりのある父母に限らず、もう少し広く象徴的なものととらえてもいいのではと思います。もちろん父親、母親は最も身近で重要な存在ではありますが、父親的存在、母親的存在あるいは父親的関わり、母親的な関わりをする他者もまた子どもたちの規範意識の形成に深く関わることは出来るのではないでしょうか。
ただしその場合、関わる他者は子どもたちにとって重要な存在であることがかかせません。そうでなければ子どもたちの心に葛藤など生まれるわけはないからです。
たとえば子どもが何らかの事情で「してはいけないこと」をしてしまったとします。このとき本人にとって重要でない人に注意されたり、制度的な懲罰をされても表面的に従うだけで本人の規範意識の形成にはつながらないと思います。逆に許されたとしても懺悔の気持ちなど生まれず規範意識の形成にはつながらないでしょう。
本人にとって重要な人に厳格な対応をされたり、逆に受容してもらうことではじめて同一視や、懺悔といった心の動きが生まれるのです。
ですから今の日本で子どもたちの規範意識が薄れてきているのが事実だとすれば、それはとりもなおさず子どもたちと大人の関係性が薄れてきていること、表面的な対応に終始してしっかりと向き合っていないことが原因なのではないでしょうか。
時代の風潮なのかもしれませんが、危惧すべきことだと思います。
初期のころの不登校の子どもたちは「こうあるべきだ」「こうあってはいけない」という規範意識を強く持っていました。そのため高い理想を掲げそれを目指して頑張るが、どうしても無理をするのでやがて疲弊していき、達成できない自分を責めたり、さまざまな身体症状を発して登校できなくなるという過程をたどることが多かったのです。
これに対し、今のこどもたちはそれほど規範意識が高いわけではなく、不登校の理由は多様化し、中心は友人関係の問題に移行してきたように思います。
ただ「規範意識の低下」は不登校の子どもたちに限った話ではなく、もっと広い日本の子どもたち全体の傾向のようにも感じます。試しにネットで「規範意識、低下」と検索すると、現状や対策をめぐって多くの議論が展開されており、多くの人、特に教育関係の人たちの間ではこうした問題意識が共有されているのではないでしょうか。
ではその原因はなにか? あるいはそもそも「規範意識」はどのように形成されるのか?
今月はそのことについて少し考えてみようと思います。
まず問題とする「規範意識」について明確にしておきます。ここで言う「規範意識」は単に「決められた規則を守る」という「遵法精神」のことではなく、自らの内面に形成された「こうあるべき」「こうあってはならない」という行動を律する道徳律のことで、「ルールを守る」という意味での規範意識はその一部をなすものです。
人間はこうした規範意識を成長の過程で身に付けていくわけですが、その形成過程の解明に先鞭をつけたのが心理学者フロイトです。
フロイトは人間の心にはエス(無意識)、自我、超自我の三つの領域があり、このうちの超自我が道徳律を担う部分だとしました。そしてこの超自我がどのように形成されるかを説明したのがエディプス・コンプレックスといわれるものです。
以下、話の流れに必要な範囲で簡単に説明しておきます。
3歳〜6歳の男児は母親に対する愛情から母を独占したいという欲求を抱きます。そのため競争相手としての父親に敵意や対抗心を持つようになりますが、同時に強大な存在としての父親から罰せられるのではないかという恐怖を抱きます。この葛藤を克服するために男児は乗り越えられない存在としての父親に、敵対心を抱きながらも「父親のようになろう」と同一視するようになります。この過程で父親の価値観、行動原理を自らの中に取り込むことで超自我が形成されていくというのです。
重要なのは「敵対心と恐怖を抱きながらも同一視する」という複雑な心理過程(コンプレックス)だと思います。(日本ではコンプレックスというと「劣等感」のようにとらえている傾向がありますが、一筋縄にはいかない複雑な心の状態を意味するととらえるべきでしょう。)
フロイトは女児の場合についても説明していますが、男児に比べ超自我の形成が不完全であるとされるなど、どうしても男性中心、父性原理に偏った印象はぬぐいきれません。エディプス・コンプレックスはフロイトの生きた時代背景、個人的経験が色濃く反映されたもので、一面の真理はついているもののこれだけでは普遍的な理論にはなりえない印象です。
そのためフロイトの理論を補完したり、批判するさまざまな理論が形成されて行きます。
その中の一つにフロイトの弟子である心理学者の古澤平作が提唱した東洋人の心理過程を説明する「阿闍世(アジャセ)コンプレックス」があります。
これについても簡単に説明しておきます。
阿闍世は仏典に出てくる古代インドのマガタ国の王子です。阿闍世はその出生の経緯から自らの存在価値を認められていないと思い母親である韋提希(イダイケ)夫人を恨み、攻撃するようになります。ところが阿闍世が重病にかかったとき、攻撃されていた韋提希夫人が献身的な看病をしたことでなんとか阿闍世は回復します。これにより阿闍世の中に自らを許し受け入れてくれた母に対する「もうしわけなかった」という懺悔の心が芽生えていきます。
このように母親との関係の中で受け入れて欲しいという欲求と、それがかなえられないことから来る恨みと攻撃、そうした葛藤を経た後での許しと受容という複雑な心理過程の中で罪悪意識が形成されていくとするのです。
厳格な父性原理をベースとするエディプス・コンプレックスと受容する母性原理をベースとする阿闍世コンプレックスはどちらか一方が正しいわけでなく、お互いを補うものととらえるべきで、子どもたちの状況によりそれぞれの見方をすればよいのではないでしょうか。
また規範意識の形成は当然この二つの過程に限られるわけではなく、じっさい子どもたちはさまざまな時期に、さまざまな形や経緯でで自らの規範意識を形成しくのでしょう。
ただ、この二つは今もなお子どもたちの規範意識の形成にいくつかの大切な視点を与えていると思っています。
まず重要なのはどちらの理論も子どもたちの規範意識は心の複雑な動き、相反する感情が揺れ動く葛藤を経て初めて形成されるとしていることです。規範は親が一方的に教え込むものではなく、親との深い関係のなかで子どもの中に生まれてくるものだということです。
そしてどちらの理論も直接には子どもと父親、母親との関係に関するものですが、これについては生物学的なつながりのある父母に限らず、もう少し広く象徴的なものととらえてもいいのではと思います。もちろん父親、母親は最も身近で重要な存在ではありますが、父親的存在、母親的存在あるいは父親的関わり、母親的な関わりをする他者もまた子どもたちの規範意識の形成に深く関わることは出来るのではないでしょうか。
ただしその場合、関わる他者は子どもたちにとって重要な存在であることがかかせません。そうでなければ子どもたちの心に葛藤など生まれるわけはないからです。
たとえば子どもが何らかの事情で「してはいけないこと」をしてしまったとします。このとき本人にとって重要でない人に注意されたり、制度的な懲罰をされても表面的に従うだけで本人の規範意識の形成にはつながらないと思います。逆に許されたとしても懺悔の気持ちなど生まれず規範意識の形成にはつながらないでしょう。
本人にとって重要な人に厳格な対応をされたり、逆に受容してもらうことではじめて同一視や、懺悔といった心の動きが生まれるのです。
ですから今の日本で子どもたちの規範意識が薄れてきているのが事実だとすれば、それはとりもなおさず子どもたちと大人の関係性が薄れてきていること、表面的な対応に終始してしっかりと向き合っていないことが原因なのではないでしょうか。
時代の風潮なのかもしれませんが、危惧すべきことだと思います。